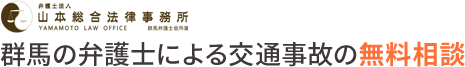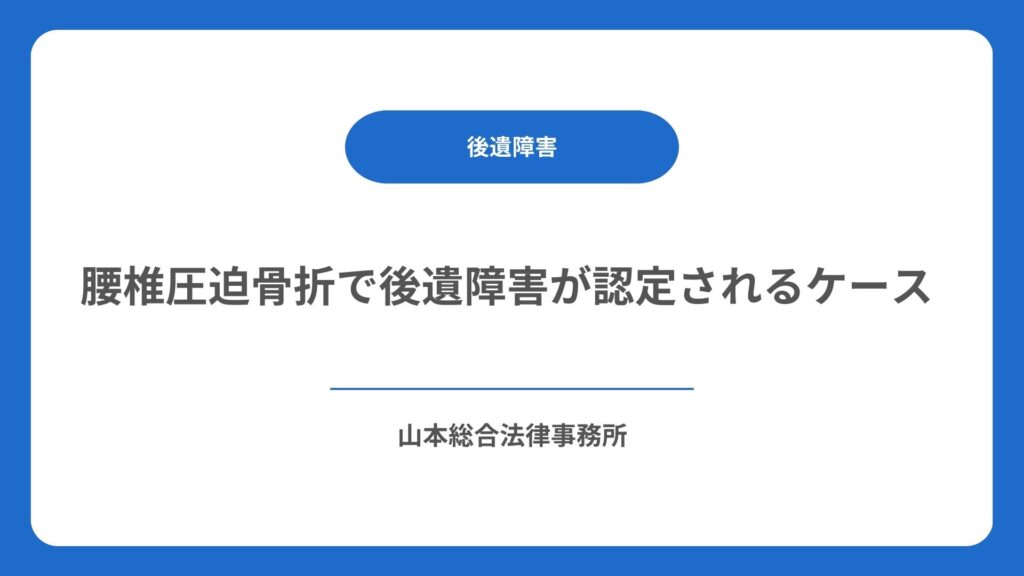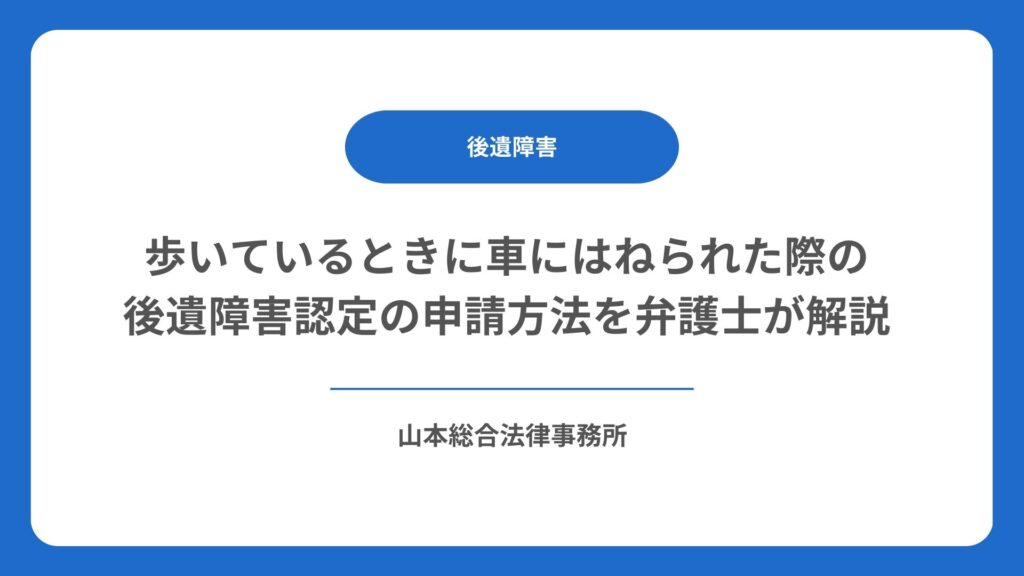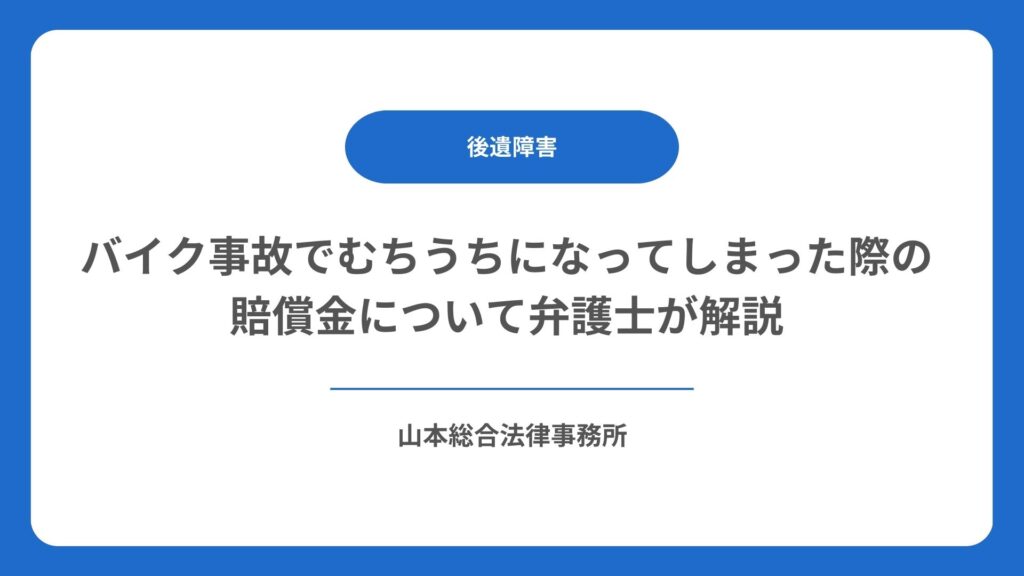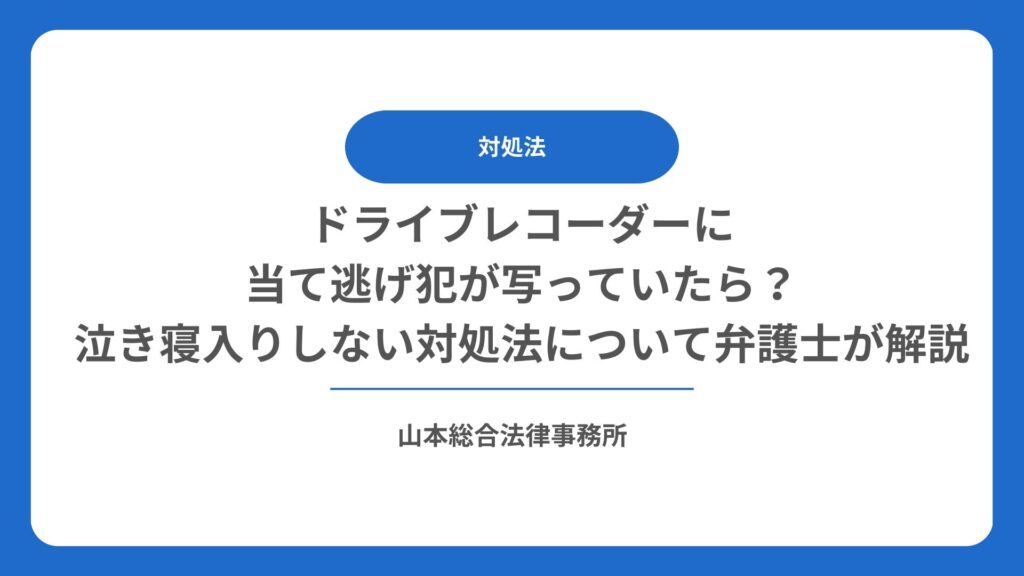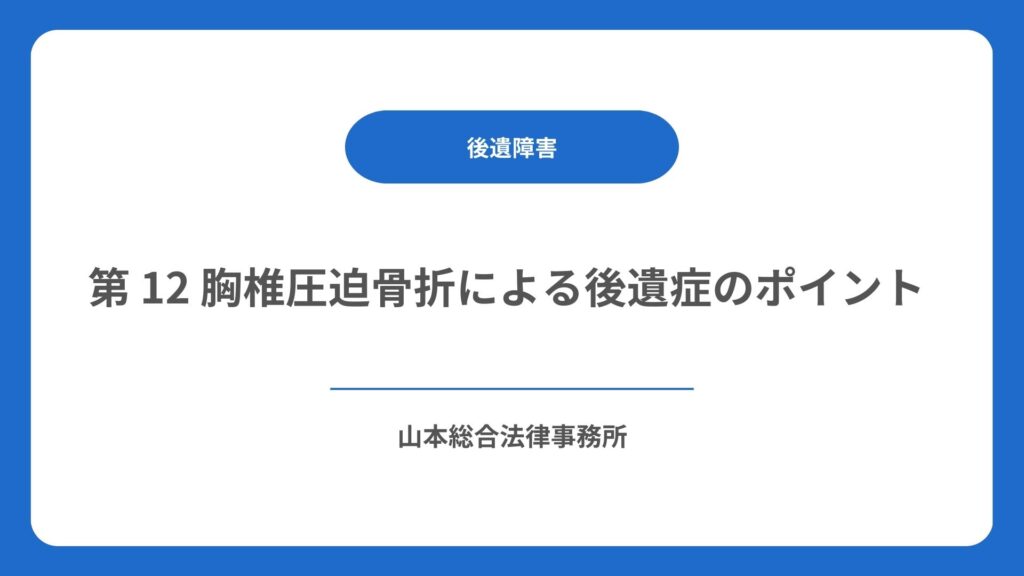バイク事故で症状固定になってしまったら?後遺障害等級認定の申請方法や注意点を弁護士が解説
- 執筆者弁護士 山本哲也
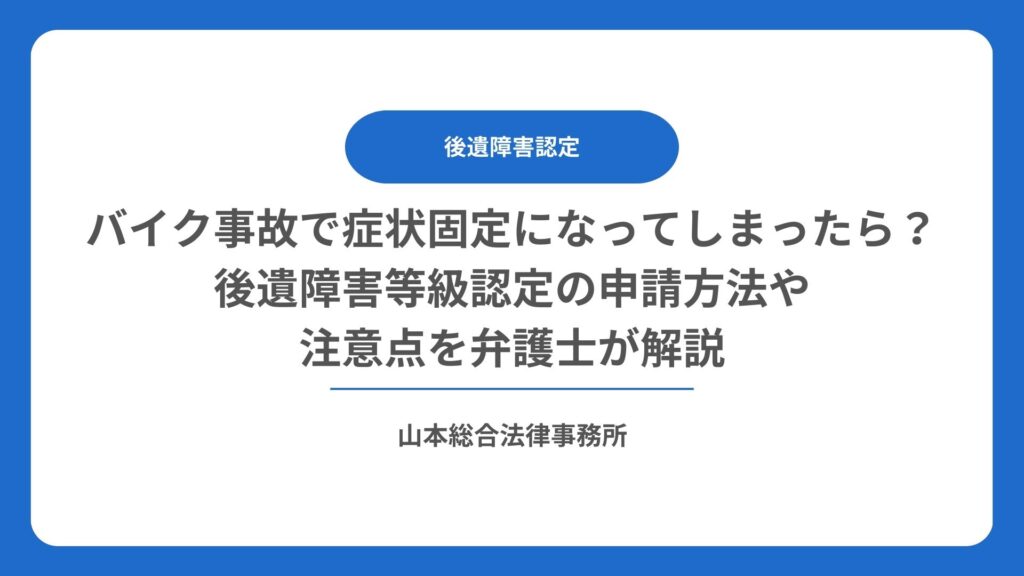
バイク事故は、ほぼ生身の状態で衝撃を受けますので、重篤な怪我につながりやすく治療を続けても痛みやしびれが完全には回復しないケースも少なくありません。
医師から「症状固定」と診断されると、それ以上治療を続けても改善が見込めない状態とされるため、今後は後遺障害の有無や程度を判断していくことになります。
このとき重要になるのが「後遺障害等級認定」です。
後遺障害が認定されるかどうかで、受け取れる損害賠償額は大きく変わります。
しかし、申請の方法や注意点を理解していなければ、適正な補償を受けられないリスクもありますので、後遺障害等級認定の申請方法や注意点を正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、バイク事故で症状固定となった場合の流れや後遺障害等級認定の申請方法、注意点についてわかりやすく解説します。
目次
はじめに|症状固定とは
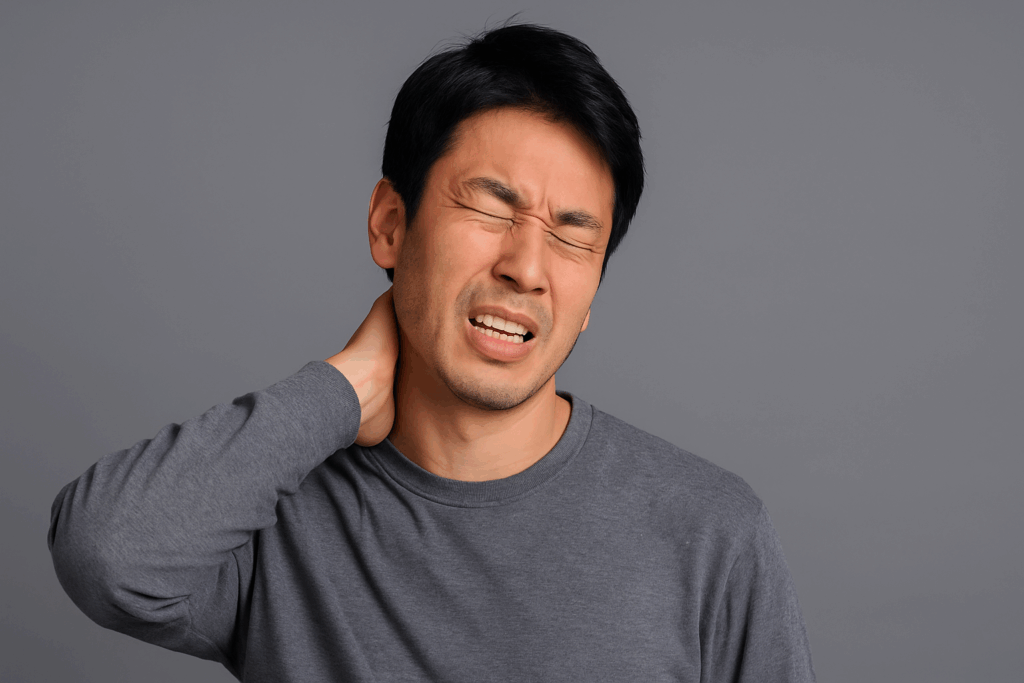
バイク事故に遭ったあと、治療を続けても症状が完全には改善せず、痛みやしびれが残ってしまうことがあります。
このような場合、医師から「症状固定」と診断されることがあります。
症状固定とは、それ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指します。
決して「ケガが完治した」という意味ではなく、医学的に治療の効果が頭打ちとなり、後遺症として症状が残っている状態を意味します。
症状固定の診断がなされると、治療費の支払いは一旦終了し、今後は「後遺障害」にあたるかどうかの判断へと移ります。
後遺障害が認められるかどうかは、その後の損害賠償請求に大きく影響する重要なポイントです。
特に、バイク事故は、自動車事故に比べて身体へのダメージが大きく、骨折や神経損傷といった後遺症が残るケースが少なくありません。
そのため、症状固定の診断後にどのような流れで後遺障害等級認定を受け、適正な賠償を求めていくかを理解しておくことが非常に大切です。
以下では、症状固定から後遺障害等級認定の流れ、申請方法、注意点をわかりやすく解説していきます。
交通事故に巻き込まれてから解決までの道のり

バイク事故に遭った直後から賠償金の支払いを受けるまでには、いくつかの重要なステップがあります。以下では、事故発生から解決に至るまでの一般的な流れを確認しておきましょう。
交通事故発生
事故が発生したら、まずは冷静に状況を確認し、以下の対応を行うようにしてください。事故直後の対応を誤ると、その後の損害賠償請求に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
警察へ連絡
どんなに軽い事故でも必ず警察に通報し、交通事故証明書を発行してもらいます。証明書は、保険金請求や裁判の際に欠かせない書類です。
保険会社への報告
あなたが加入している任意保険会社へ速やかに事故発生を報告します。保険会社に報告すれば、レッカー車や代車の手配、相手方との対応などを代わりに行ってくれます。
病院に通う
事故後は、できるだけ早く医療機関を受診し、医師から完治または症状固定と診断されるまで治療を続けます。
主治医から症状固定の診断
一定期間治療を続けても症状が改善せず、「これ以上治療を続けても回復は難しい」と医師が判断した場合、「症状固定」と診断されます。
ここから先は、加害者側の保険会社からの治療費の支払いは終了し、後遺障害の有無を判断する段階に移ります。
後遺障害等級の認定を受ける
症状固定後、後遺症が残った場合には後遺障害等級認定の申請を行います。
症状に応じた後遺障害等級認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が可能になり、賠償額の大幅な増額につながります。
加害者の保険会社から損害賠償額の提示
後遺障害等級が認定されると、加害者側の保険会社から損害賠償額の提示がなされます。
示談が成立したら損害賠償を受け取る
保険会社から提示された賠償額に納得ができれば示談を締結し、損害賠償金を受け取ります。
ただし、保険会社から提示される金額は、裁判になった場合に認定される金額(裁判所基準)に比べて、低い金額であることが多いため、そのまま示談に応じるのではなく、しっかりと交渉をすることが重要です。
被害者自身で交渉をしても、満足いく金額まで増額できるケースは少ないため、保険会社との示談交渉は弁護士に任せるべきです。
示談が決裂したら法的機関へ
保険会社の交渉の結果、納得いく金額が提示されないときは、裁判所に訴訟提起を行います。
訴訟手続きになると専門的な知識や経験がなければ対応が難しいため、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼して進めていくようにしましょう。
後遺障害等級認定の申請方法
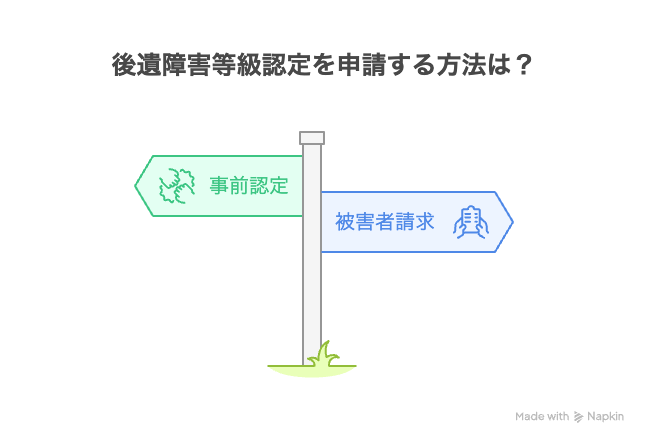
症状固定の診断を受けたあとに行うのが、後遺障害等級認定の申請です。申請方法には大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
以下では、それぞれの申請方法の概要とメリット・デメリットを説明します。
事前認定
事前認定とは、加害者側の任意保険会社が被害者に代わって必要書類を集め、自賠責保険に申請する方法です。
事前認定の最大のメリットは、手続きの手間がほとんどかからない点にあります。
被害者自身が診断書や事故証明書を取り寄せる必要は基本的になく、保険会社が主導して申請を行うため、手続きの流れもスムーズです。
事故後の治療や生活に追われている被害者にとっては、大きな負担軽減につながります。
しかし、加害者側の保険会社の立場としては賠償額をできるだけ低く抑えたい意向があるため、被害者にとって有利な資料が十分に収集・提出されない可能性があります。
その結果、本来認められるべき等級よりも低い評価となり、受け取れる損害賠償が少なくなってしまうリスクがあります。また、一度不十分な資料で認定が下されると、その後の異議申立てでも不利になりかねません。
したがって、手続きが簡便だからといって安易に任せてしまうと、納得のいく結果を得られないおそれがあるのです。
被害者請求
被害者請求とは、被害者が自ら必要書類を整え、自賠責保険に直接申請する方法です。
被害者請求のメリットは、自分に有利な資料を積極的に添付できる点にあります。
たとえば、主治医に依頼して詳細な後遺障害診断書を書いてもらったり、MRIやレントゲン画像を追加で提出したりすることで、症状の深刻さをより正確に伝えることが可能です。
これにより、適正な等級認定を受けられる可能性が高まり、納得感のある賠償額につながりやすいのが大きなメリットです。
ただし、被害者請求にはデメリットもあります。診断書や事故証明など必要書類の収集には多くの手間がかかり、場合によっては医師に追加で記載を依頼する必要もあります。
また、後遺障害認定の基準や必要な資料について専門的な知識が求められるため、準備が不十分だと本来認められるべき等級が認定されないリスクもあります。
そのため、被害者請求を選択する場合には、交通事故案件に詳しい弁護士のサポートを受けながら、適切な資料を揃え、正当な評価を得られる可能性を高めることが重要です。
後遺障害等級認定の申請をする際の注意点
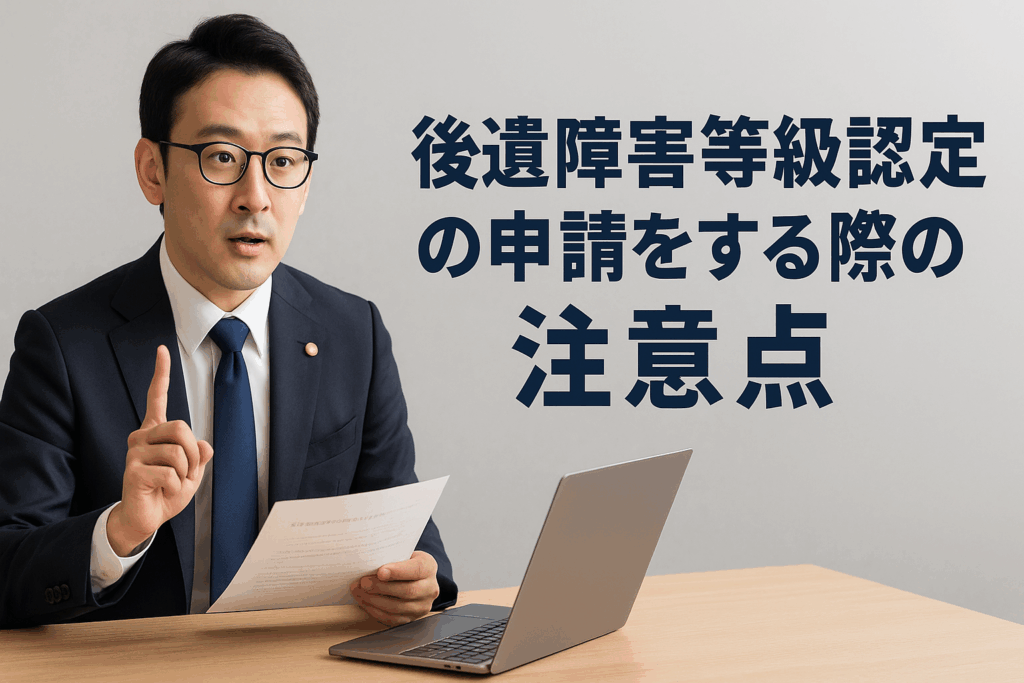
適正な後遺障害等級認定を受けるためには、単に申請書類を提出するだけでは不十分です。
医師の診断や通院状況、資料の準備の仕方によって結果が左右されるため、以下の点に注意が必要です。
医師の診断書や検査資料を十分に準備すること
後遺障害等級認定手続きにおいてもっとも重要なのは医師の診断書と検査資料です。
診断書の記載が不十分だと、実際の症状の重さが正しく伝わらず、低い等級しか認められないおそれがあります。
特に、神経障害や可動域制限などは、MRI画像や関節可動域測定の結果など客観的なデータが重視されます。
そのため、主治医に詳細な診断書を依頼することや必要に応じて再検査を受けて資料を充実させることが大切です。
診断書や検査資料の質によって損害賠償額が大きく変わるため、軽視してはいけません。
医師の指示に従って定期的・継続的に通院すること
後遺障害の有無を判断する際には、事故後の通院状況も重要視されます。
治療を自己判断で中断したり、通院間隔が長く空いたりすると「症状が軽い」と判断され、不利な等級認定につながる可能性があります。
反対に、医師の指示を守って定期的かつ継続的に通院している記録は、症状の持続性や治療の必要性を裏付ける有力な証拠となります。
通院実績は診療録に残るため、後遺障害等級認定の際に大きな意味を持ちます。
途中で自己判断せず、医師の指示に従って治療を続けることが適正な認定を受けるための基本です。
認定結果に不服があれば異議申立てを検討すること
後遺障害等級認定の結果に納得できない場合には、異議申立てを行うことが可能です。
認定結果が不当に低いと感じたときには、新たな検査資料を提出したり、診断書をより詳細に書き直してもらうことで結果が覆る可能性があります。
ただし、異議申立ては単に「不満だから」という理由では認められず、追加の資料や医学的根拠を補強することが欠かせません。
そのため、専門知識を持つ弁護士や医師と協力して手続きを進めることが重要です。
適切に準備を行えば、再認定で等級が上がるケースも少なくありません。
後遺障害等級認定の申請は弁護士にご依頼を

後遺障害等級認定は、提出書類の内容や通院状況によって結果が大きく変わります。
ご自身で対応すると不十分な資料のまま低い等級しか認められないケースも少なくありません。
適正な等級を獲得し、将来にわたる補償を確保するためには、交通事故に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士法人山本総合法律事務所では、後遺障害認定の申請から異議申立て、示談交渉まで豊富な実績があります。
初回相談は無料で承っておりますので、バイク事故で症状固定と診断された方は、お早めにご相談ください。