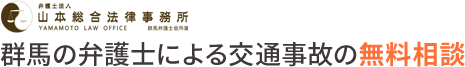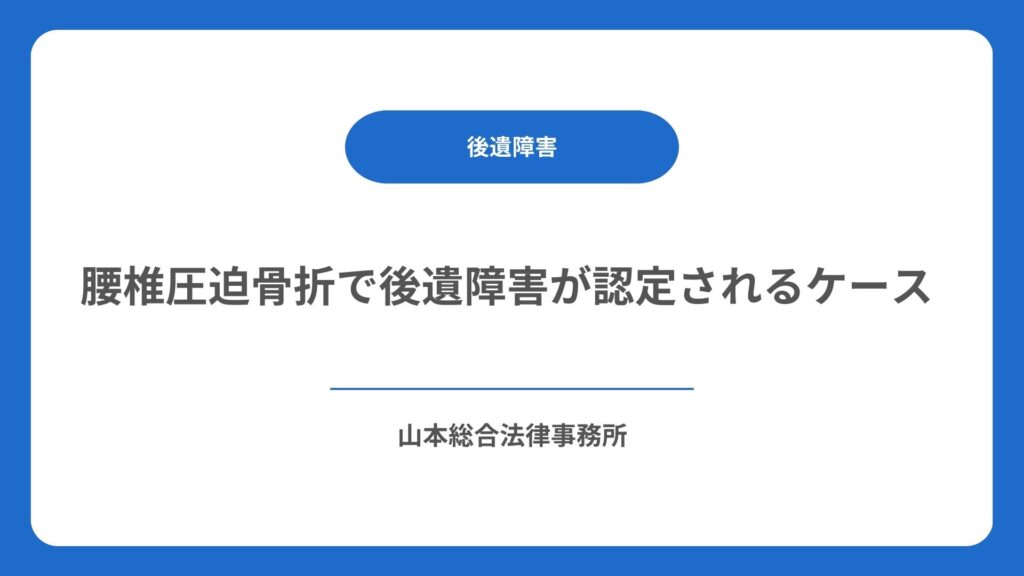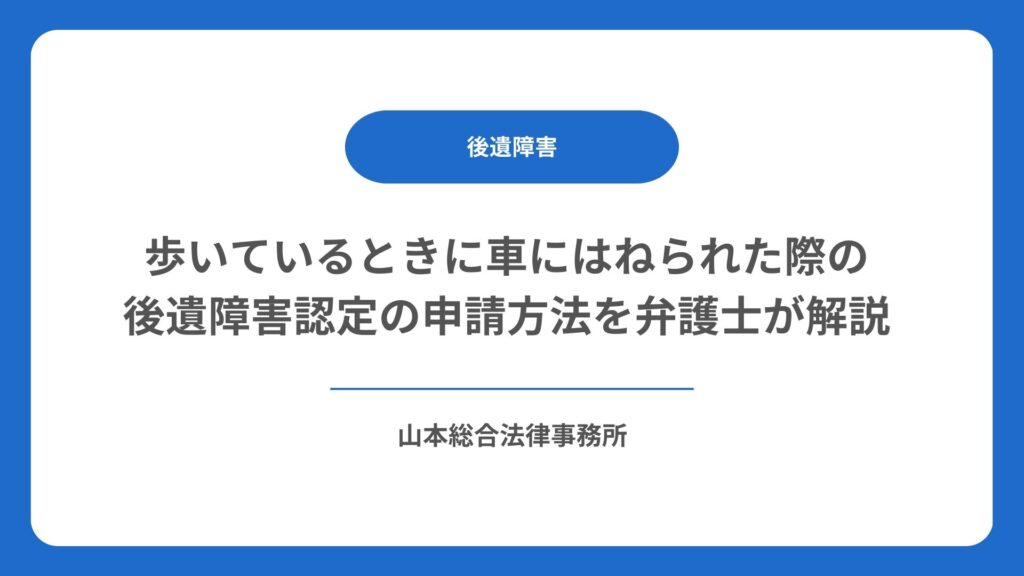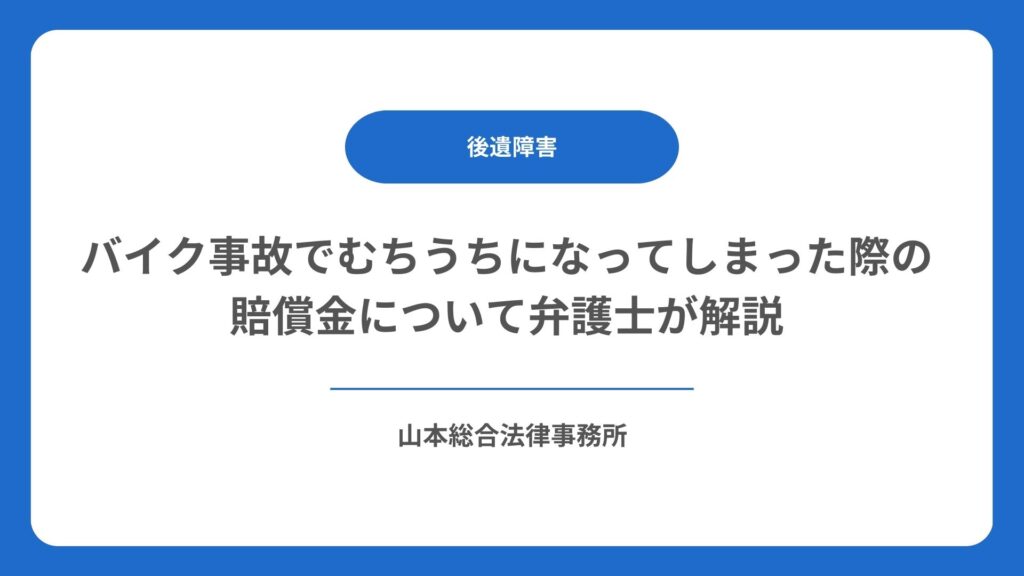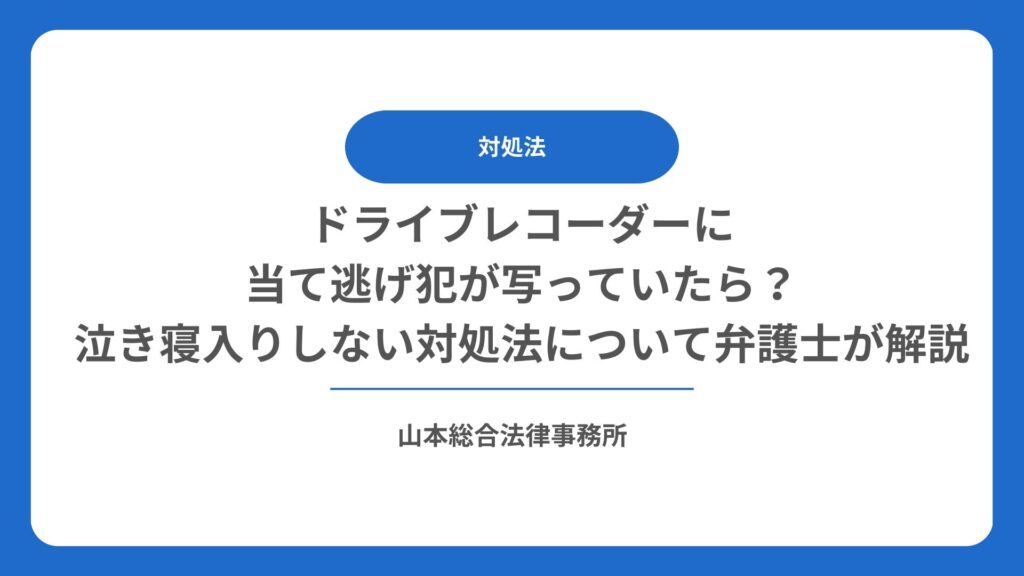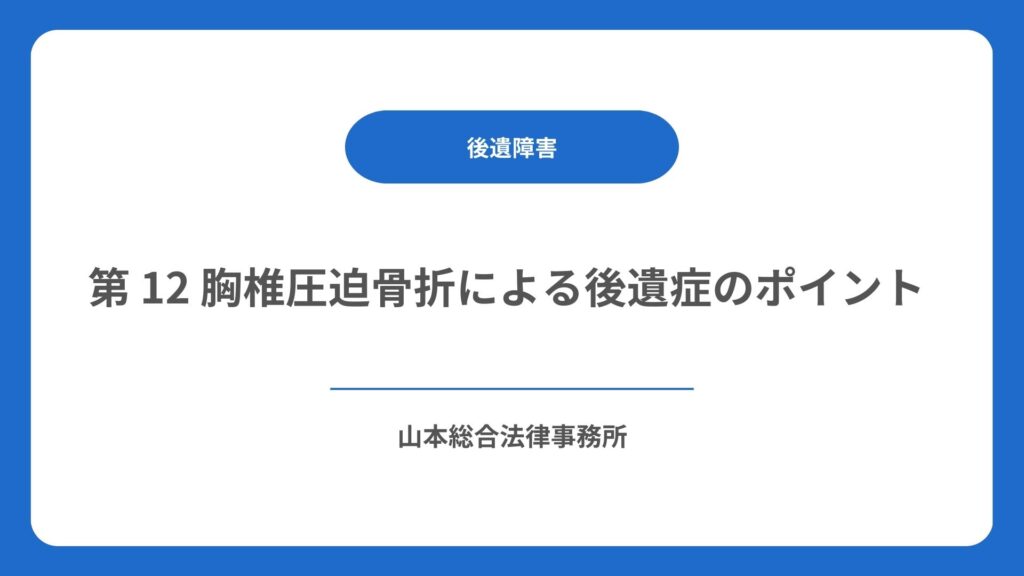【後遺障害11級とは?】症状の具体例・認定基準・補償内容まで弁護士が解説
- 執筆者弁護士 山本哲也

交通事故による怪我で後遺症が残ってしまったときは、後遺障害等級認定を受けて賠償金を増額できる可能性があります。
後遺障害等級は1級から14級まであり、症状の内容や程度に応じて何級に認定されるかが異なってきます。
今回は、後遺障害11級の症状と認定基準について解説するとともに、11級に認定された場合の補償内容や、認定を受けるためのポイントなどもご紹介します。
目次
後遺障害等級 11 級とは

後遺障害11級とは、1級から14級まである後遺障害等級のうち、軽い方から4番目の等級のことです。後遺障害等級11級の中でも障害の部位や程度に応じて1号から10号に区分されています。
以下では、後遺障害11級の認定基準や具体的な症状、他の等級との違いについて解説します。
11 級の概要と認定基準
後遺障害11級に該当する症状と認定基準は、以下のとおりです。
| 等級 | 症状の概要 |
|---|---|
| 11級1号 | 両眼に著しい調節機能障害または運動障害 |
| 11級2号 | 両まぶたの運動障害 |
| 11級3号 | 片まぶたの欠損 |
| 11級4号 | 10歯以上に補綴(差し歯・入れ歯等) |
| 11級5号 | 両耳の聴力が1m以上で小声を解せない程度 |
| 11級6号 | 片耳の聴力が40cm以上で普通の声が聞き取れない程度 |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
| 11級8号 | 指(人差し指・中指・薬指)を1本失う |
| 11級9号 | 足の指(親指含む2本以上)の用を廃する |
| 11級10号 | 胸腹部臓器の障害で労務に支障があるもの |
具体的な症状例
次に、後遺障害11級の1号から10号に該当する具体的な症状を説明します。
11級1号|両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
11級1号は、両目が以下のいずれかの状態になった場合に認定されます。
・瞳の調節力が半分以下になった
・注視野が半分以下になった
11級2号|両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級2号は、両目が以下のいずれかになった場合に認定されます。
・目を開いたときに瞳孔部分がまぶたによって完全に覆われている
・目を閉じたときに角膜が完全に覆われない
11級3号|1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号は、片目のまぶたが欠損したことにより、目を閉じたときに角膜が完全に覆われない状態になった場合に認定されます。
11級4号|10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号は、10本以上の歯を失うか、歯冠部の4分の3以上が欠け、義歯やクラウンなどで補った場合に認定されます。
11級5号|両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
11級5号は、両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上となった場合に認定されます。
11級6号|1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
11級6号は、片耳が以下のいずれかになった場合に認定されます。
・平均純音聴力レベルが70デシベル以上80デシベル未満
・平均純音聴力レベルが50デシベル以上かつ最高明瞭度が50%以下
11級7号|脊柱に変形を残すもの
11級7号は、脊柱が以下のいずれかになった場合に認定されます。
・脊椎圧迫骨折を残していることがX線写真などで確認できる
・脊椎固定術が行われた(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収された場合を除く)
・3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けた
11級8号|1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
11級8号は、片手の人差し指、中指、薬指のうち1本が、以下のいずれかになった場合に認定されます。
・中手骨(指の付け根の関節と手首の間の骨)または基節骨(指の第2関節と付け根の関節の間の骨)で切り離した
・近位指節間関節(第2関節)において基節骨と中節骨(指の第1関節と第2関節の間の骨)を切り離した
11級9号|1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11級9号は、片足の親指を含む2本以上4本以下の指が、以下のいずれかになった場合に認定されます。
・親指の末端骨(先端の骨)が半分以下になった
・親指の指節間関節(指の付け根の関節)の可動域が通常の半分以下になった
・親指以外の足指が中節骨もしくは基節骨で切り離されたか、遠位指節間関節(第1関節)または近位指節間関節で切り離された
・親指以外の足指の中足指節間関節(指の付け根の関節)または近位指節間関節(第2関節)の可動域が半分以下になった
11級10号|胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
11級10号は、胸腹部臓器(呼吸器、循環器、消化器、泌尿器)の機能に障害が残り、労働はできるものの業務にかなりの差し障りがある場合に認定されます。
他の等級との違い
後遺障害等級は、同じような内容の症状であっても、症状の程度によって認定される等級が以下のように変わってきます。
| 11級の項目 | 認定基準 | より軽い等級 | より重い等級 |
|---|---|---|---|
| 11級1号 | 両眼の調節機能または運動障害 | 12級1号(片目) | ― |
| 11級2号 | 両まぶたに著しい運動障害 | 12級2号(片目) | ― |
| 11級3号 | 片まぶたの欠損 | 14級1号(片目の一部欠損)
13級4号(両目の一部欠損) |
9級4号(両目) |
| 11級4号 | 10歯以上の補綴 | 14級2号(3~4歯)
13級5号(5~6歯) 12級3号(7~9歯) |
10級4号(14歯以上) |
| 11級5号 | 両耳で小声が1mで聞き取れない | 10級5号(普通の話声が困難)
9級7号(普通の話声が聞き取れない) |
4級3号(全失聴)
6級3号(大声が接しても聞き取れない) 7級2号(40cm以上で話声が聞き取れない) |
| 11級6号 | 片耳で40cm以上離れると話声が聞こえない | 14級3号(1m以上で小声が聞こえない)
10級6号(接して大声が聞こえない) |
6級4号(片耳全失聴+他耳40cm以下)
7級3号(片耳全失聴+他耳1m以下) 9級8号(片耳接して大声+他耳1m困難) 9級9号(片耳全失聴) |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残す | ― | 8級2号(運動障害)
6級5号(著しい変形) |
| 11級8号 | 指(人差し・中指・薬指のいずれか)を1本失う | 14級6号(他の指の一部欠損)
13級6号(小指の用廃) 13級7号(親指の一部欠損) 12級9号(小指欠損) |
9級12号(親指or他2指)
8級3号(親指+他2指 or 他3指) 7級6号(親指+他3指) 6級8号(5指 or 親指含む4指) 3級5号(両手の指全部) |
| 11級9号 | 足指(親指含む2本以上)の用廃 | 14級8号(第3足指以下1~2本)
13級10号(第2含む2本 or 3本) 12級12号(親指含む1本) |
9級15号(片足全指)
7級11号(両足全指) |
| 11級10号 | 胸腹部臓器の障害で労務に支障 | 13級11号(胸腹部臓器に機能障害あり) | 9級11号(労務制限)
7級5号(軽労務以外不可) 5級3号(軽労務も不可) 3級4号(終身労務不能) 2級2号(随時介護) 1級2号(常時介護) |
手指や足指、まぶたの欠損障害などは客観的に認定されやすいです。
しかし、その他の障害の中には、専門的な検査における測定値によって認定される等級が変わってくるものも多いので、注意が必要です。
【関連リンク】各等級ごとの解説
後遺障害等級 11 級の認定を受けるには

後遺障害等級11級の認定を受けるためには、所定の申請手続きが必要です。
申請は専門機関による審査で判断されるため、手続きの流れや準備する書類を正しく理解し、適切に進めることが重要です。
後遺障害等級の申請は、以下のようなステップで進んでいきます。
申請の流れ
- 症状固定の診断を受ける
- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
- 申請方法を選ぶ(事前認定 or 被害者請求)
- 自賠責調査事務所による審査を受ける
- 等級認定の結果通知を受け取る
- 納得できなければ異議申し立ても可能
それぞれのステップについて、以下で詳しく解説します。
STEP1:症状固定の診断を受ける
まずは、医師の判断により「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態」、すなわち「症状固定」と診断されることが必要です。
✅️ ポイント
保険会社から「もう症状固定では?」と打診されることがありますが、判断するのは医師です。焦らず、医師の指示に従って治療を続けましょう。
STEP2:後遺障害診断書を医師に作成してもらう
症状固定と診断されたら、主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。この診断書は、後遺障害等級の審査において最も重要な書類のひとつです。
✅️ 注意点
記載内容が曖昧だったり、必要な検査結果が反映されていないと、正当な等級が認定されない可能性があります。
専門性の高い医師や、後遺障害に理解のある医療機関を選ぶことが望ましいです。
STEP3:申請方法を選ぶ(事前認定 or 被害者請求)
後遺障害診断書が完成したら、2つの方法のいずれかで申請します。
【事前認定と被害者請求の違い】
| 申請方法 | 特徴 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 事前認定 | 加害者側の保険会社が書類を取りまとめて申請 | 手間がかからないが、内容を確認できず不利な判断が出る可能性も |
| 被害者請求 | 被害者自身が書類をそろえて自賠責に直接申請 | 手間はかかるが、自分で書類内容を精査でき、有利な審査が期待できる |
✅️ ポイント
適切な等級認定を得るために、「被害者請求」による申請をおすすめします。
STEP4:専門機関による審査
申請が受理されると、専門機関(損害保険料算出機構)が提出書類をもとに後遺障害等級の審査を行います。
審査には通常1〜2か月程度かかります。
【提出書類の例】
- 後遺障害診断書
- 医療検査記録(レントゲン、MRI等)
- 事故証明書
- 病院や薬局、接骨院等の通院記録 等
STEP5:後遺障害等級の認定結果が通知される
審査が終わると、後遺障害等級の認定結果が書面で通知されます。
認定された場合は、該当等級に応じた「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能となります。
STEP6:結果に不服がある場合は異議申立ても可能
もし、認定された等級に納得できない場合は、異議申立てを行い再審査を求めることが可能です。
異議申立てには専門的な知識が求められるため、交通事故・後遺障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ│認定のための手続きは、正確さと準備がカギ
後遺障害11級の認定を受けるためには、医師の診断・診断書の内容・申請方法の選択など、さまざまな要素が関係します。
一度認定されると変更が難しいため、慎重かつ丁寧に進めることが大切です。
特に適切な等級を得るためには、弁護士によるアドバイスやサポートを活用することで、納得のいく補償につながりやすくなります。
11 級に認定された場合の補償内容

後遺障害11級に認定された場合は、怪我の治療費や休業損害、慰謝料(入通院慰謝料)といった通常の損害項目に加えて、以下のような損害の賠償を請求できます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺症が残ってしまったことにより被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
この慰謝料の金額は、主に次の3つの基準のいずれかに基づいて算定されます。
📘 慰謝料の3つの算定基準
- 自賠責保険基準:国が定める最低限の補償額。保険会社が最初に提示してくることが多い。
- 任意保険基準:保険会社ごとの社内基準(非公開)。自賠責と同程度または少し高い程度の金額。
- 裁判所基準(弁護士基準):過去の裁判例に基づく最も高額な基準。弁護士を通じて請求する場合に使われる。
後遺障害11級に認定された場合、慰謝料の相場は以下のとおりです。
-
自賠責保険基準:136万円
-
裁判所基準(弁護士基準):420万円前後
加害者側の保険会社は、自賠責保険基準や任意保険基準に基づいた低い金額を提示してくることが多いのが実情です。
しかし、裁判所基準では約3倍近い金額となるため、適正な慰謝料を得るためには、裁判所基準での請求を目指すことが重要です。
そのためには、交通事故に強い弁護士のサポートを受けることが大きな力となります。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害の影響で労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入の一部が失われてしまうことに対する賠償金です。
たとえば、事故前と同じように働くことが難しくなった場合や、就ける職種が制限された場合など、その影響を金銭的に補填する意味があります。
後遺障害逸失利益の金額は、以下の計算式によって算出します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
📘 計算に使う3つの要素
- 基礎収入:事故前年の年収や、賃金センサス(平均賃金統計)をもとに設定されます。
- 労働能力喪失率:後遺障害等級ごとに目安があり、11級では20%が一般的とされています。
- ライプニッツ係数:将来の損害額を現在価値に換算するための係数で、被害者の年齢によって数値が変動します。
計算例
例えば、以下のようなケースでは、後遺障害逸失利益は次のように計算されます:
-
症状固定時の年齢:40歳
-
事故前年の年収:500万円
-
労働能力喪失率:20%
-
ライプニッツ係数:18.327(40歳の場合)
【計算式】
500万円 × 0.2 × 18.327 = 約1,832万7,000円
後遺障害等級 11 級の獲得のために注意すべきこと

後遺障害11級を獲得するためには、以下の点に注意が必要です。
医師の指示に従い十分な治療を受ける
後遺障害等級認定の対象となる障害は、十分な治療を受けても改善せず残ったものに限られます。そのため、医師が症状固定の診断を下すまで、治療を継続することが重要です。
治療中に加害者側の保険会社が「そろそろ症状固定にしましょう」と打診してくることもありますが、症状固定かどうかを判断するのは保険会社ではなく医師です。必ず医師の指示に従って、十分な治療を受けるべきです。
専門性の高い医療機関で精密な検査を行う
後遺障害11級の対象となる障害の中には、専門的な検査における測定値が重要視されるものも多いです。そのため、検査の精度が低ければ適正な後遺障害等級認定を受けられないおそれがあります。
症状の内容に応じて専門性の高い医療機関へ通院し、精密な検査を行っておくことが大切です。
まとめ│後遺障害11級に該当しそうなら弁護士に相談を
後遺障害11級は、労務への支障が生じる後遺症として適正な補償が受けられる等級です。
適正な等級に認定されるためには、医師の診断書の内容や検査数値の精度、書類の提出方法などが重要となります。
不安な点がある場合は、後遺障害に詳しい弁護士へ早めに相談することで、適切な対応と補償を受けられる可能性が高まります。
交通事故の後遺症でお悩みの方は、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士法人山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所の事例
併合11級が認定され、約1,900万円を獲得した事例 *別途労災にて約400万円の支給あり
優先道路を走行中、右折車と出会い頭に衝突してしまった30代公務員の方が、当事務所にご依頼後、後遺障害等級「併合11級」の認定を受け、約1,900万円の賠償金を得た事例です。
疼痛による就労への支障を丁寧に主張した結果、定年までの逸失利益が認められ、裁判所基準に沿った高額示談となりました。
事故直後からのご相談が、結果的に適正な賠償へとつながりました。
第3腰椎の圧迫骨折及び腰部の疼痛で11級7号が認定され、賠償金として2077万円を獲得した事例
センターラインを越えてきた対向車との衝突事故により、第3腰椎圧迫骨折と腰部の疼痛を負った40代会社員の方が、後遺障害等級11級7号を獲得し、総額2,077万円の賠償金を得た事例です。
細かな賃金規定を反映させた休業損害の算定や、逸失利益の労働能力喪失率を20%と認めさせる交渉に成功。
ご本人様の詳細な情報提供と協力のもと、的確な資料作成と粘り強い交渉で高額賠償を実現しました。
10代学生の自転車事故につき、胸椎圧迫骨折で11級7号が認定され、裁判で約1800万円が補償された事例
高崎市在住の10代学生が自転車で走行中に後方から車に接触され、胸椎圧迫骨折を負った事故により、後遺障害11級7号が認定されました。
交渉段階では相手保険会社の提示額が低く、裁判により主張を立証した結果、約1,800万円の高額賠償を獲得。
ご本人の症状や生活への影響を丁寧に証明し、交渉時の約3倍の金額を勝ち取った解決事例です。