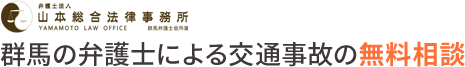執筆者弁護士 山本哲也
後遺障害慰謝料とは?
交通事故によるケガで後遺障害が認定された場合に、その精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことを「後遺障害慰謝料」といいます。

交通事故に遭ったあと、治療を続けても痛みやしびれが残ってしまうことがあります。
このような「治らない症状」が残ったとき、重要になるのが「後遺障害」の認定と、それに基づく「後遺障害慰謝料」の請求です。
このコラムでは、後遺障害慰謝料の仕組みや金額の相場、保険会社との交渉の注意点に加え、後遺症との違いや逸失利益・将来介護費用など、賠償全体の視点からわかりやすく解説します。
「後遺症」と「後遺障害」は何が違う?
まず押さえておきたいのが、「後遺症」と「後遺障害」の違いです。
後遺症(医学的な用語)
ケガや病気の治療を終えても残る症状のこと。
例:首の痛み・しびれ・可動域の制限など
後遺障害(法的な概念)
後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づいて等級が認定されたもの。
慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求できる。
つまり、「症状が残っている」だけでは損害賠償の対象にならず、「後遺障害」として等級認定されることが必要です。
後遺障害慰謝料とは?
交通事故で負ったケガで後遺症が「後遺障害」として認定された場合に請求できる、精神的苦痛に対する慰謝料が「後遺障害慰謝料」です。
後遺障害には症状の度合いによって1級~14級の等級が定められています。1級が一番症状が重く、14級は主にむちうち等の症状で認定されることが多いです。
症状の重い等級は後遺障害慰謝料も高額になる傾向があります。
後遺障害慰謝料の金額相場
慰謝料の金額は、「どの基準で算定されるか」によって大きく異なります。主な基準は以下の3つです。
| 基準名 | 特徴 | 14級慰謝料 | 1級慰謝料 |
|---|---|---|---|
| 自賠責基準 | 法律上の最低限。保険会社が使う最低ライン。 | 約32万円 | 約1,100万円 |
| 任意保険基準 | 保険会社ごとの基準。公表されていない。 | 非公開 | 非公開 |
| 裁判基準(弁護士基準) | 裁判例に基づく最も高額な基準。弁護士が請求する場合のみ使える基準。 | 約110万円 | 約2,800万円 |
【等級別】後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料を自賠責保険基準と弁護士基準で比較すると下記の通りとなります。
任意保険基準は非公開となっているため、ここでは取り上げていません。
また、後遺障害慰謝料の金額は介護が必要なほど重度の後遺障害であるか否かによっても、基準が異なります。
介護が必要な場合
| 等級 | 自賠責基準(慰謝料) | 弁護士基準(裁判基準) |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
| 2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
介護を要さない場合
| 等級 | 慰謝料額(自賠責基準) | 慰謝料額(裁判基準) |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害が認定されたら、慰謝料以外にも請求できるものがある
◆ 後遺障害による「逸失利益」
後遺障害によって労働能力が低下した場合、将来得られるはずだった収入が減ってしまうことがあります。
この失われた将来の収入を金銭的に評価したものが「逸失利益」です。
逸失利益は下記の計算式で算出されます。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に応じたライプニッツ係数
たとえば、12級の認定を受けた会社員が、年収500万円で就労可能年数が25年ある場合、数百万円〜1,000万円以上の逸失利益が認められることもあります。
◆ 重度後遺障害の場合は「将来介護費用」も請求可能
1級・2級などの重い後遺障害では、将来の生活に介護が必要となる場合があります。この場合、以下のような介護費用を請求できます。
- 専門の介護人を雇う費用(訪問介護・施設など)
- 家族による介護が前提でも、無償介護分を一定金額として評価
こうした将来介護費用も、まとめて一括で損害賠償請求の対象になります。
後遺障害慰謝料を請求するための流れ
1.症状固定の診断
医師から「これ以上良くならない状態」と診断されたタイミングで、後遺障害の認定手続きに進みます。
2.後遺障害等級認定の申請
次のどちらかの方法で後遺障害等級認定の申請を行います。
- 加害者側の保険会社に任せる「事前認定」
- 自分で必要書類を揃える「被害者請求」(弁護士に依頼も可能)
適正な等級を認定してもらうためには「被害者請求」をおすすめします。
3.等級認定結果の通知
審査期間で審査が行われ、等級が決定します。審査には2~3ヶ月を要することもあります。
一定の基準に満たないと判断されると、後遺障害には当てはまらない「非該当」と判断される場合もあります。
結果に納得がいかない場合、「異議申立」で再審査をしてもらう方法もあります。
4.慰謝料の交渉・請求
後遺障害等級の結果をもとに請求金額を算定し、保険会社との交渉を行います。
弁護士に依頼すれば裁判基準で請求が可能です。
後遺障害慰謝料の増額を目指すためのポイント
通院の継続と診断書の記載内容
医師に症状をしっかり伝え、必要な検査(MRIなど)を受けておくことが重要です。
画像や診断結果の提出
後遺障害の存在を客観的に証明できる資料を揃えることで、認定されやすくなります。
弁護士への早期相談
書類の不備や交渉の失敗による不利益を避けるためにも、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
後遺障害慰謝料についてまとめると、下記の通りです。
- 後遺障害が認定された場合、精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」を請求できます。
- 保険会社提示の金額が妥当かどうかを判断するためには、裁判基準(弁護士基準)との比較が重要です。
- 弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額や等級認定の異議申し立ても可能となり、適正な賠償を受けられる可能性が高まります。