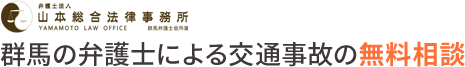執筆者弁護士 山本哲也
後遺障害認定に対する異議申立について
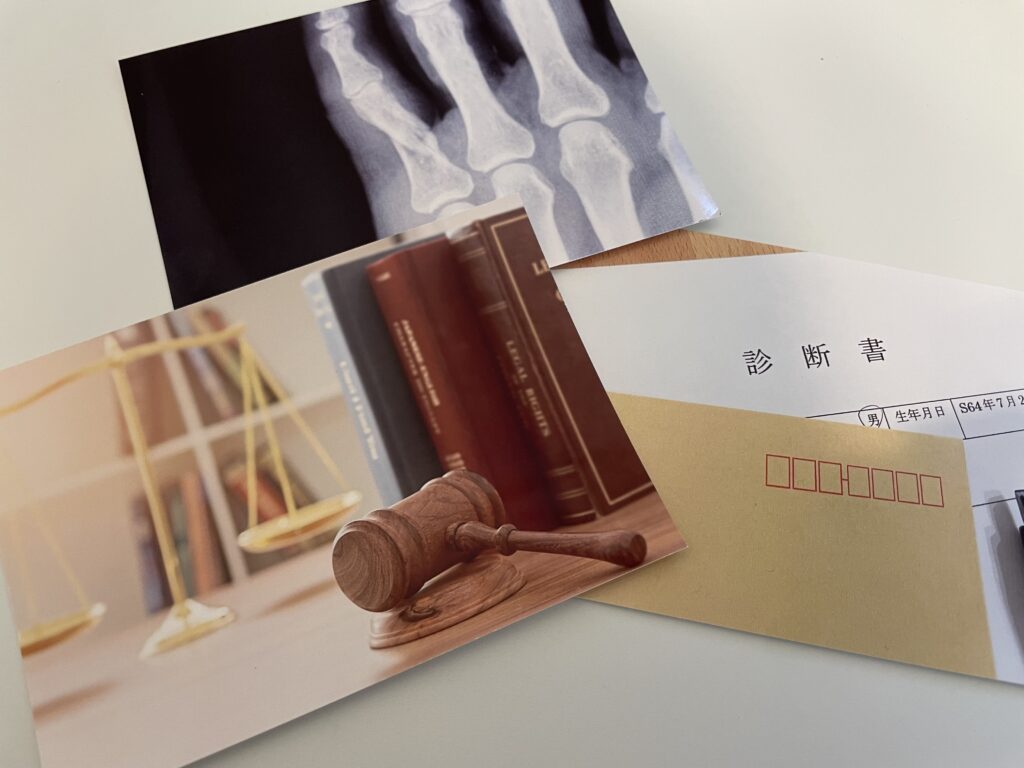
後遺障害申請をしても、必ずしも適正な等級が認定されるとは限りません。
適正な等級が認定されない理由には主に以下のようなものがあります。
- 後遺障害を立証するために必要な検査を行っていない。
治療のための検査と後遺障害の立証に必要な検査は必ずしも一致するとは限りません。主治医が障害の認定実務に詳しくなかったり、診療科目が違うために必要な検査が行われない場合があります。被害者側は、主治医に理由を説明して検査を依頼するなどの行動を取る必要があります。 - 後遺障害診断書の記載が適切でない
後遺障害診断書の記載が必ずしも十分とはいえない場合や、ていねいに記載してあるが肝心な点が抜けている場合などがあります。 - 審査側の認定が間違っている
審査を行う側も人間ですから、見落としや間違いをすることもあり得ます。したがって、認定結果を鵜呑みにせず、きちんと確認することが必要です。
後遺障害等級認定に納得のいかない場合は異議申し立てをすることができます。
もっとも、異議申立てを行うという段階では、(後遺障害等級別表の)後遺障害に該当するか、該当するとしてどの等級に該当するかについて一度判断がされているという状況にあるということになります。
したがって、異議申立てというのは既になされた判断を覆すだけの根拠が必要になるということになります。
そのため、新たに何らの資料を提出することもなく、既になされた等級認定について不満を述べるだけでは、異議申立てが認められる可能性は低いと言わざるを得ません。
効果的に異議申立てを行うためには、非該当と判断された理由をきちんと理解し、分析する必要があります。非該当と判断された理由は、認定結果に併せて書面で通知されます。
非該当と判断された理由の分析が終わったら、次に、その理由に対してどのように反論すべきか、反論の根拠となる新たな資料としてどのようなものかをあるのかを考え、新たに必要となる資料を収集し、これを添付して異議申立を行うことになるでしょう。
新たに準備する資料としては、例えば、高度な医療水準であると評価を受けている医療機関の専門医による新たな診断書や、主治医の意見書などを用意することが考えられます。また、最初に後遺障害申請の手続きをした際に未提出だった各種の検査結果や、新たに行った検査結果も、必要に応じて提出します.
新たな資料と共に提出する異議申立書には、収集した証拠に基づいて反論すべき点や、新たに提出する医師の所見などの説明、現在の生活における支障、事故の状況などを記載します。
以上、異議申立についてご説明してきましたが、一度「非該当」という判断がなされているわけですから、その判断を覆すだけの理由がない限り、異議申立により後遺障害が認められることはないと思われます。そのため、異議申立はそう簡単には認められません。
ですから、まずは、異議申立をあてにするのではなく、最初の後遺障害認定で適切な認定が受けられるように十分な準備をすべきであると思います。
異議申立て後の流れについては、初回の申請では認定結果が出るまでの期間は1~2か月程度のことが多いですが、異議申立の場合にはそれよりも時間がかかることが多いようです。時には3か月以上かかる場合もあります。
以上、後遺障害認定の異議申し立てについてご説明させていただきました。
弊所では後遺障害の等級認定に向けて手厚いサポートを行っておりますので、ぜひご相談ください。