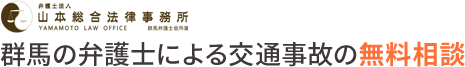執筆者弁護士 山本哲也
後遺障害逸失利益の計算にあたって、労働能力喪失率はどのように決まるのですか?
現在の実務上、労働能力喪失率表により後遺障害等級ごとに定められていますが、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、労働能力喪失率表の喪失率とは異なった判断になることがあり得ます。
交通事故による受傷が原因で、後遺障害が残ることがあります。そして、その後遺障害により、仕事に支障が生じ、収入が減少してしまうこともあります。
この点、交通事故による受傷が原因で、後遺障害が残り、労働能力が低下して収入が減少するような場合には、その補償を受けることができます(これを後遺障害逸失利益といいます)。
具体的な計算方法としては、現在の実務上、「基礎収入」に「労働能力喪失率」及び「労働能力喪失期間」を乗じた金額となります。
この点、「労働能力喪失率」は、後遺障害による労働能力の喪失の程度を表すものであり、労働能力喪失率表(労働省労働基準局通牒という規定)において、後遺障害等級ごとに定められています。
そして、この労働能力喪失率表は、判断の画一性や公平性から事実上の基準となっています。それゆえ、労働能力喪失率表の喪失率を上回る労働能力の喪失があるという場合には、積極的に主張していく必要があります。
具体的には、現在の裁判実務上、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、労働能力喪失率表の喪失率以上の労働能力の喪失があるか否かを判断していくので、上記各事実を主張して、労働能力喪失率表の喪失率を上回る労働能力の喪失がある旨を主張していくことになります。
なお、鎖骨、骨盤骨、脊柱の変形等の変形障害や、醜状障害等については、その等級に対応した労働能力の喪失率が実態に合致していない場合があり得ると考える立場から、労働能力喪失率表どおりの喪失率を認めない旨の主張がなされ、実際にその主張を認めた裁判例もあります。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。